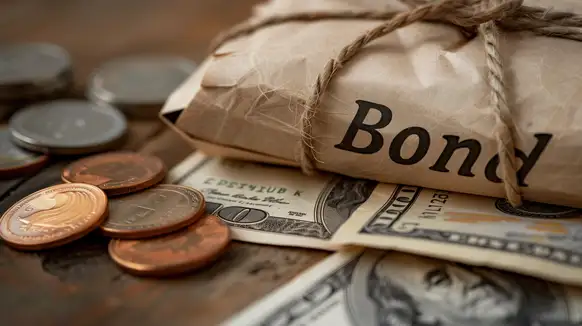投資を始めたいと考えている方の中には、「株式投資はリスクが高そうで怖い」「でも預金だけでは資産が増えない」という悩みを抱えてる方もいらっしゃるかもしれません。そのような方に注目していただきたいのが債券投資です。
債券投資が初めての方は、まず「債券市場の仕組みをわかりやすく解説!債券投資のメリット・デメリットも紹介」の記事から読むことをおすすめします。債券の基本的な仕組みや特徴を理解してから、こちらの記事をお読みいただくことで、より深い理解が得られます。
本記事では、債券投資において押さえておくべき勘所、キーポイントとなる「債券価格と金利の関係性」と「イールドカーブ」について解説します。そのうえで、プロの機関投資家も実践しているリスクに配慮した債券運用戦略の代表例をご紹介していきます。
これらの知識を身につけることで、債券投資のリスクをコントロールし、安定した収益を目指すことができるようになることでしょう。
債券投資で理解すべき2つのキーポイント:債券の価格変動とイールドカーブ
債券投資を行う際には、株式投資と異なった固有の仕組みを理解することが欠かせません。
債券(利付債券)は、確定した利息額(利金)を定期的に得て満期に元本が償還されますので、「安全な投資」と言われますが、償還までの期間中には市場金利の変動によって債券価格が大きく動くリスクがあります。
このリスクを適切に管理し、収益機会として活用するためには、2つのキーポイント「債券価格と金利の関係性」と「イールドカーブ」について理解しておく必要があります。
債券価格と金利の関係性:初心者が知るべき債券投資のキーポイント①
ここでは、債券価格がなぜ変動するのか、その変動をどのように活用できるのかについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
債券投資において最も重要な原理は、「債券価格と市場金利が逆方向に動く」、即ち、「市場金利が上がると債券価格が下がる、市場金利が下がると債券価格が上がる」という関係性です。
債券の利率が固定される仕組みと価格変動の関係
債券の基本的な仕組みから確認していきましょう。債券を発行する際、発行体は「表面利率」と呼ばれる満期まで固定した利率を設定します。例えば、国が表面利率2%の10年国債を額面100万円で発行した場合(実際には、新発の国債でも発行時の金利動向により額面価格と購入価格が異なってきます。)、その国債を購入した人には毎年2万円の利息(利金)が支払われ、10年後に元本100万円が償還されることになります。ここで重要なのは、債券発行後に市場金利が変動しても、債券の「表面利率は変わらない」ということです。
例えば、表面利率2%の債券を発行した後に市場金利が3%に上昇した場合について、考えてみましょう。その時点で新規発行される債券は3%の表面利率ですから、2%の債券がそれと等価となる最終利回り(満期までの残存期間を保有し続けた場合の利回り)を確保するには、表面利率の2%は変えられませんので、債券価格(=額面の評価額)を下げなければならないことになります。
反対に市場金利が1%に低下した場合には、表面利率2%の債券は債券価格が上昇することになります。
この価格変動メカニズムによって、債券投資家は金利低下局面では値上がり益を、金利上昇局面では値下がり損失を経験することになります。ですので、債券投資を行う際には、現在の金利水準と将来の金利動向を十分に検討することが重要になります。
さて、債券価格と市場金利の関係の基本を押さえたところで、次に、重要な用語として「デュレーション」について説明していきたいと思います。
価格と金利変動の関係:デュレーション(金利感応度)の基礎知識
債券投資で用いられる「デュレーション」という言葉には2つの意味合いがあります。
1つは「債券投資をキャッシュフローで捉えたときの投資開始から利金・元本を受け取って満期償還されるまでの加重平均期間」(「マコーレ・デュレーション」といいます。)、もう1つは「債券価格が金利変動に対してどの程度敏感に反応するかを示す指標(金利感応度)」(「修正デュレーション」といいます。)です。
修正デュレーションは、金利が1%変動した時に債券価格がどれだけ変動するかを示す数値として活用されています。
デュレーションの計算式
$$
\Large D_{mac} = \frac{\sum_{t=1}^{n} \frac{t \times C_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^{n} \frac{C_t}{(1+r)^t}}
$$
$$
= \frac{\text{(利金・元本の現在価値 × 回収年数)の合計}}{\text{(利金・元本の現在価値)の合計}}
$$
- Dmac : マコーレ・デュレーション
- t : 各キャッシュフローが発生する時点
- Ct: t 期に発生するキャッシュフロー(利金、償還元本)
- r : 最終利回り
- n: 満期までの期間(年)
$$
\Large \text{修正デュレーション} = – \frac{D_{mac}}{1+r}
$$
例えば、デュレーションが5年の債券を保有している場合、金利が1%上昇すると債券価格は約5%下落し、逆に金利が1%低下すると債券価格は約5%上昇することになります。
デュレーションは債券の満期までの期間だけでなく、クーポン(利金)の支払い頻度や利率によっても変化します。一般的に、満期が長い債券ほどデュレーションが大きくなり、金利変動の影響を受けやすくなる特徴があります。また、クーポン利率が低い債券ほど、デュレーションが大きくなる傾向があります。
日本国債10年物を例にした具体的な価格変動シミュレーション

実際の数値例を用いて、金利変動が債券価格に与える影響を確認してみましょう。
表面利率1%、残存期間10年の日本国債を額面100万円で購入したケースを想定します。この債券のデュレーションは約9.5年となります。
購入時点で市場金利が1%だった場合、この債券の理論価格は額面と同じ100万円となります。しかし、購入後に市場金利が0.5%に低下した場合、デュレーションの計算式に基づくと、債券価格は約4.7%上昇し、104万7,000円程度になります。反対に市場金利が1.5%に上昇した場合、債券価格は約4.7%下落し、95万3,000円程度になります。このように、0.5%の金利変動でも、10年債では約5万円近くの価格変動が生じるのです。
このシミュレーションから分かるように、債券投資では金利変動リスクを適切に評価し、自分のリスク許容度に合った投資期間を選択することが極めて重要になります。
では、次に債券投資のもう1つのキーポイントとなる「イールドカーブ」について説明していきたいと思います。
イールドカーブ:初心者が知るべき債券投資のキーポイント②

「イールドカーブ」とは、端的にいうと、複数の残存期間が異なる同種の債券について、横軸に残存期間、縦軸に各債券の利回りを取ってグラフ化したものです。
このイールドカーブの形状は、市場参加者の経済見通しや金融政策への期待を反映した重要な指標として機能しており、その変化のパターンを読み解くことで、将来の金利動向や経済情勢を予測する手がかりを得ることができます。
イールドカーブの読み方と将来予測への活用
通常の経済状況では、長期債の利回りが短期債よりも高くなり、イールドカーブが右肩上がりとなる「順イールド」という状態になります。これは、資金が拘束される期間が長くなるほど、より高いリターンが要求されるという合理的な判断を反映したものです。
順イールド(右上がりの曲線)が急勾配(スティープ化)となる場合には、市場参加者の間で将来の金利上昇期待が高まっていることを示しています。これは、経済成長の加速やインフレ率が上昇するとの見方が強まっていることを背景としており、中央銀行による利上げ政策が予想される状況です。このような環境では、長期債投資は価格下落リスクが高まるため注意が必要です。
一方、イールドカーブが平坦化(フラット化)している場合は、長期金利と短期金利の差が縮小しており、将来の金利上昇期待が限定的であることを示しています。これは、経済成長の鈍化や中央銀行の慎重な政策スタンスを反映したものと見ることができます。
最も注意しなければならないのは「逆イールド(右下がりの曲線)」の発生です。これは長期金利が短期金利を下回る異常な状態で、景気後退の前兆として現れることが多いとされています。専門家の間では「リセッション・シグナル」とも呼ばれ、リスク回避の動きが強まる傾向があります。
ここまで、債券投資のキーポイントとして「債券価格と金利の関係性」、「イールドカーブ」の説明をしてきましたが、以下では、この2つのキーポイントを踏まえた債券運用戦略について見ていきたいと思います。
プロが実践する債券運用戦略:リスク管理から収益向上まで
債券投資において、金利が変動していく中で安定的な収益を得ようとすると、単純に債券を購入して満期まで保有するだけでは必ずしも十分とはいえません。プロの投資家は、金利変動リスクを適切にコントロールしながら、市場の状況に応じて収益機会を最大化する様々な戦略を活用しています。
ここでは、リスクコントロールを勘案した債券運用戦略(イミュニゼーション戦略、ロールダウン戦略、バーベル戦略・ラダー戦略)について、それぞれのメリット・デメリットを含めて解説していきます。
これらの戦略は決して複雑なものではなく、基本的な仕組みを理解すれば個人投資家でも実践することができます。ただし、ご自身の投資目的やリスク許容度、資金の性格に応じて最適な戦略を選択することが大切です。また、これらの戦略は相互に排他的なものではなく、組み合わせて活用することも可能です。
投資期間とデュレーションを一致させるイミュニゼーション戦略
イミュニゼーション戦略は、金利変動リスクを中和(イミュニゼーション:免疫化)させる運用手法です。この戦略の核心は、債券運用の加重平均投資期間をマコーレ・デュレーションに一致させることで金利収入の増減額と債券価格の変動額を釣り合うようにし、市中金利が上昇しても下落しても、目標とする収益を確保できるようにすることにあります。
この戦略の最大のメリットは、金利変動に関係なく目標収益を達成できる確実性の高さです。年金基金や保険会社などの機関投資家が、将来の支払い義務に備えるために多用している手法でもあります。一方で、デメリットとしては、金利低下時の値上がり益を一部放棄することになる点や、定期的な残高調整(リバランス)が必要になる点が挙げられます。
イールドカーブの形状変化を利用するロールダウン戦略
ロールダウン戦略は、イールドカーブの順イールド(右上がり)状態が長期にわたって継続すると見込まれるときに、時間の経過とともに保有する長期債の残存期間が短くなるに連れて債券価格が徐々に上昇することを利用した収益獲得手法です。イールドカーブの勾配が急な年限の債券を選択することで、より大きなロールダウン効果が期待できます。
例えば、5年債の利回りが1.5%、10年債の利回りが2%という状況を想定しましょう。利回り2%の10年債を購入して5年間保有し続けると、この債券は残存期間5年の債券となります。保有した5年間で金利環境がまったく変わらなければ、この債券の利回りは5年債の水準である1.5%まで低下し、その分だけ債券価格が上昇することになります。
ただし、この戦略にはいくつかのリスクがあります。市場金利が上昇した場合には、ロールダウン効果を上回る価格下落が生じる可能性があります。また、イールドカーブがフラット化したり逆イールドになった場合には、期待した収益がまったく得られなくなる可能性もあります。
ポートフォリオ分散を最適化するバーベル戦略・ラダー戦略
バーベル戦略とラダー戦略は、いずれも投資期間を分散することでリスクを軽減し、収益の安定化を図る手法です。これらの戦略は、金利変動の予測が困難な環境において特に有効とされています。
バーベル戦略は、短期債と長期債を組み合わせる(例えば、投資資金の50%を2年債、残り50%を10年債に投資する)手法です。
この戦略は、短期債により流動性(容易に資金化できること)と金利上昇への対応力を確保しつつ、長期債により高い利回りを追求することを狙いとしています。金利上昇局面では短期債の再投資効果を活用し、金利下落局面では長期債の値上がり益を享受することができます。
ラダー戦略は、満期の異なる複数の債券を階段状(ラダー)に配置する手法です。例えば、1年債から10年債まで各年限に均等に投資し、毎年満期を迎える債券の元本を新たな10年債に再投資していきます。この戦略により、金利変動の影響を平準化し、安定的な収益を確保することができます。
一歩進んだ債券投資を目指そう
今回のまとめ
今回は、債券投資が安全な投資資産といわれるのは満期保有を前提としていて、保有期間中には絶えず利回り・債券価格が変化していること、債券投資のキーポイントとして「債券価格と金利の関係性(デュレーション)」「イールドカーブ」、そして、それらを活かしリスク対応を図った債券運用戦略について学んできました。
単に債券を満期まで保有することに留まらず、今回学んだことを踏まえ、さら一歩進んでデュレーションの考え方を活用し、保有期間中の金利変動リスクにも備えた債券投資を目指してみてはいかがでしょうか。
継続的な学習とリスク管理の重要性
債券投資に限らず資産運用全般にいえることですが、継続的な情報収集・学習と適切なリスク管理が大切です。
経済環境、景気動向や金融政策の変更等から、金融市場は常に動いており、ご自身で保有する債券や他の金融資産の価値も絶えず変化します。世の中がどのように動いているのか、それがご自身にとってどのような影響があるのか、継続的な情報収集・分析に努め、学習していくことが望まれます。
また、リスク管理の観点からは、ご自身の投資目的、投資可能金額・期間、リスク許容度を明確にすることを出発点として、金融資産の損益状況を定期的に確認し、投資方針の見直しを行って資産構成を調整していくことが長期的な成功へと導いてくれることでしょう。
※投資はお客様自身の判断と責任において行ってください。