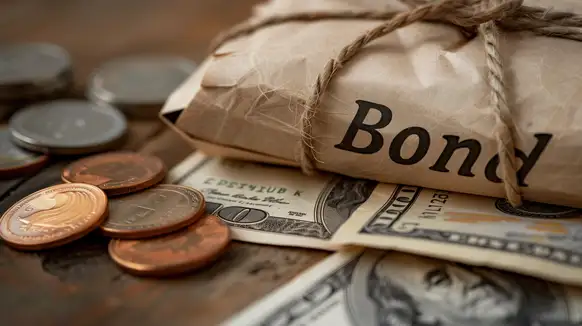長期で資産形成を目指すiDeCoでは、運用商品の選び方が重要です。しかし、みなさんは最初に選んだ商品をそのままにしていませんか?市場環境やライフステージの変化に応じて資産配分を見直すことが重要です。その際に役立つのが「スイッチング」という仕組みです。ただし、iDeCoは通常の投資信託と異なり、年齢制限や拠出額制約といった独自のルールがあるため、それらを考慮した戦略的なスイッチングが不可欠です。そこで本記事では、iDeCoにおけるスイッチングの活用術を紹介していきます。
iDeCoにおけるスイッチングとは?基本的な仕組みと一般的な投資との違い
個人型確定拠出年金(以下、iDeCo)は老後資金を形成するための重要な制度ですが、一般的な投資とは異なる特殊な制約があるからこそ、異なる戦略が必要になります。特に、運用商品を変更する「スイッチング」については、正しい知識を身につけておかなければ、せっかくの長期運用のメリットを活かせない可能性があります。
iDeCoとスイッチングの基本説明
iDeCoとは、「個人型確定拠出年金」の略称で、公的年金とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つとして位置づけられています。加入は任意となっており、申込から掛金の拠出、掛金運用の全てを自身で行う制度です。最も重要な特徴として、月々5,000円から積み立てができ、原則として60歳(または65歳)まで引き出すことができません。つまり、一度拠出した資金は長期間にわたって運用し続けることになります。この長期運用が前提となる点が、iDeCoの大きな特徴といえるでしょう。iDeCoのさらなる詳しい説明については下の記事が役に立ちます。

一方のスイッチングとは、現在保有している運用商品を売却してその売却代金で別の商品を購入するという二つの手続きが一回でできる仕組みのことです。例えば、これまで国内株式の投資信託で運用していた資産を売却し、その資金で債券の投資信託を購入するといった操作を指します。
なぜiDeCo特有の戦略が必要なのか
iDeCoが一般的な投資と大きく異なる点は、年齢制限と拠出額制限という2つの制約があることです。これらの制約により、リスクとリターンの考え方が従来の投資とは異なってきます。まず年齢制限について説明しましょう。iDeCoは原則60歳まで引き出しができないため、一般的な投資信託のように「いつでも現金化できる」わけではありません。また、現在の年齢によって運用期間が決まります。20代の方であれば30年以上の運用期間がありますが、50代後半の方では運用期間は10年を切ることになります。この運用期間の違いにより、リスクの取り方や運用戦略を調整する必要があります。次に拠出額制限です。iDeCoには加入者の属性によって月々の拠出限度額が決められており、転職や企業年金制度の変更によって拠出可能額が変わることがあります。一般的な投資と異なり、投資額を決められた金額以内に押さえる必要があるということです。
60歳まで引き出せないからこそ重要!年齢別iDeCoスイッチング戦略

前章で触れたように、iDeCoは原則60歳まで引き出しができません。この制約があるからこそ、年齢に応じたスイッチング戦略が重要になります。ここで紹介する戦略はあくまで一つの例ですので、実際は読者のみなさんの環境に応じて最適な戦略を考えていきましょう。
20-30代:長期運用を前提としたスイッチング戦略
20代から30代の方は、60歳まで30年以上の運用期間を確保できるため、基本的には「スイッチングしない」ことが正解となると考えられます。なぜならばこの年代では、時間を味方につけた長期投資のメリットを最大限活用することが重要になり得るからです。長期投資において最も有効な方法の一つとして、価格が下落した時により多くの口数を購入できるドルコスト平均法があります。一時的な運用成績の悪化を理由にスイッチングを行うよりも、継続して積立投資を行う方が結果的に資産形成にとってプラスになる可能性が高いのです。
ただし、例外的にスイッチングを検討すべき状況もあります。投資信託の純資産総額が継続的に減少し、運用体制に問題が生じている場合や、信託報酬などのコストが類似商品と比較して明らかに高い場合は、運用コストの低い商品への変更を検討する価値があります。
40-50代前半:受取時期を意識し始める時のスイッチング
40代から50代前半の方は、受取開始まで10年から20年程度の期間があり、まだ積極的な運用が可能な一方で、受取時期を意識し始める必要があります。この時期には、年1回の定期見直しによるリバランスの重要性が高まります。リバランスとは、当初設定した資産配分が市場の変動により崩れた際に、元の配分に戻す作業です。例えば、株式の比率が想定以上に高くなった場合、スイッチングによって株式型投信を売却し、債券型投信を購入することで、資産配分を想定どおりに戻すことができます。
またこの年代では、キャリアの変化に応じた運用方針の調整も視野に入ってくるかもしれません。収入が安定している場合はリスク資産の比率を高めより多くのリターンを狙う、逆に収入が不安定になった場合は安定的な運用への転換を検討するなどの戦略が考えられます。ただし、頻繁な変更は運用効率を下げるため、年1回程度の見直しに留めることが適切です。
50代後半:受取直前期のリスク軽減スイッチング
50代後半になると、受取開始まで10年を切るため、段階的なリスク軽減が重要な戦略となるでしょう。例えば、受取開始5年前から株式の比重を徐々に下げ、債券やバランス型ファンドの比率を高めていく戦略などが考えられます。また、受取時の税制を考慮した商品選択も重要です。iDeCoの受取時には、一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用されるため、受取方法に適した商品構成を検討することが50代後半における重要な戦略といえるでしょう。
拠出限度額の制約下でのスイッチング
前章では年齢別のスイッチング戦略について解説してきましたが、iDeCoにはもう一つ重要な制約があります。それが拠出限度額です。iDeCoには拠出限度額があり、転職や企業年金制度の変更で拠出可能額が変わることがあります。拠出額の変更は、単に積立額が増減するだけではなく、ポートフォリオ全体のバランスに影響を与えるため、適切な対応策を講じる必要があります。
拠出額増額時のポートフォリオ調整方法
政府広報オンラインによると、2024年12月から、企業年金のうち確定給付企業年金や共済等の他制度に加入している方のiDeCoの掛金の上限額(拠出限度額)が、月額12,000円から月額20,000円に引き上げられました。今後もこのような変更が実施される可能性はあります。拠出額が増額される場合、増額分をどのように配分するかが重要です。既存の配分比率を維持する方法と、既存資産のスイッチングと組み合わせた調整方法とがあります。例えば、株式の比率が想定以上に高くなっている場合、増額分は債券に多く配分し、同時に既存の株式資産の一部を債券にスイッチングすることで、全体のバランスを調整できます。また、拠出額増額のタイミングでバランス型ファンドから個別ファンドへの切り替えを検討することも有効です。拠出額が増えた場合は、より運用コストの低い個別のインデックスファンドを組み合わせることで、運用効率を向上させることができるでしょう。
拠出額減額時のポートフォリオ調整方法
転職や企業年金制度の変更により、拠出可能額が減額する場合もあります。そうした環境の変化の中で、例えば「拠出可能額は減少するが運用効率は維持したい」などという運用計画を立てることもあるでしょう。この場合には、既存の積立額を調整し、さらに既存資産のスイッチングを活用してより積極的な運用に振り向けることで、運用効率を維持できます。拠出可能額が減少する場合は、拠出先の商品の優先順位付けも重要です。一般的には、信託報酬が低く、長期的な成長が期待できる商品を優先し、コストが高い商品の拠出を減らすことが適切です。
転職時の拠出可能額変化への対応
転職は人生やキャリアにおける重要なライフイベントですが、iDeCoの拠出可能額にも大きな影響を与えます。自営業者から会社員になった場合は、月額68,000円から23,000円への減額となり、逆に、会社員から自営業者になった場合は拠出可能額が大幅に増加します。こうした拠出可能額の大幅な変更を受けて、転職を機にiDeCoの運用方針の全面的な見直しを行う場合もあるでしょう。しかし、転職をした場合は単に拠出可能額の変更だけでなく、ライフプランの見直しも含めた総合的な検討が重要になるはずです。収入や働き方が変わった場合はリスク許容度も変化している可能性があるため、スイッチングなどを用いて最適なポートフォリオを再構築することが求められるでしょう。
iDeCo特有の選択肢:スイッチング vs 配分変更 vs 放置の使い分け

ここまで年齢別や拠出額変更時のスイッチング戦略について解説してきましたが、実はiDeCoには「配分変更」という選択肢もあります。また、「何もしない」ということも立派な戦略です。これらの選択肢の、スイッチングとの使い分けを理解することで、より効率的な運用が可能になるでしょう。
3つの選択肢の使い分け基準
まず、既存の保有商品を入れ替えたい場合は「スイッチング」が適しています。これは、保有している運用商品を売却して別の商品を購入する手続きです。一方で、今後購入する商品を変更したい場合には「配分変更」が適しています。これは毎月の掛金で購入する商品の配分を変更する手続きで、既存の保有資産には影響を与えません。例えば、株式50%、債券50%で積み立てていたものを、今後は株式30%、債券70%に変更する場合などに使用します。
これら二つの選択肢は、中長期的な運用方針を見据えて、能動的にポートフォリオを調整したい場合に活用します。しかし、iDeCoは長期投資が前提です。短期的な市場の変動に対しては、焦って「スイッチング」や「配分変更」を行うのではなく、「何もしない」が最も適切な選択となることが多いものです。一時的な運用成績の悪化を理由に頻繁に変更することは、運用効率を下げる可能性があるからです。
iDeCoにおけるスイッチングのメリット・デメリット
iDeCoのスイッチングには、一般的な投資とは異なる特有のメリット・デメリットがあります。最大のメリットは、非課税でのスイッチングが可能なことです。一般的な投資信託では売却時に所得税と住民税を合わせて20.315%の税金が課されますが、iDeCoでは運用期間中の売却益に課税されないため、利益確定を税負担なしで行えます。しかし、60歳まで引き出せない制約により、スイッチング後のポートフォリオに不満が生じた場合は再びスイッチングを行ったり配分変更を申し込んだりすることになるため、事前に熟考して慎重に判断することが求められます。
頻度別の運用効率への影響
スイッチングの頻度は、運用効率に大きな影響を与えます。年1回程度の実施は適切なリバランス効果をもたらし、取引コストの影響も限定的で、長期投資の原則にも合致します。一方、月1回程度の実施は取引コストによる効率低下のリスクがあり、週1回以上の頻繁なスイッチングは明らかに長期投資の原則に反します。iDeCoは長期積立による資産形成を目的としており、頻繁な取引はドルコスト平均法の効果も減少させてしまいます。iDeCoの制約下での最適な頻度は、一般的には年1回から2回程度と考えられます。しかし、それ以上に重要なのは、「スイッチングは明確な理由と目的を持って行う」ということです。単に最近の成績が悪いからといった理由でのスイッチングは、長期的な運用成果にマイナスの影響を与える場合も多く、避けるべきでしょう。
まとめ

iDeCoにおいてスイッチングを行う際は、iDeCo特有の条件を考慮しながら運用することが重要になります。その中でも最も重要なのは、スイッチングを行う明確な理由と目的を持つことです。iDeCoは老後の資産形成を目的とした年金制度である以上、長期的な視点から運用方針を定め、制度の特徴を理解した計画的なアプローチを心がけましょう。スイッチングを利用し、今の自分に最適なポートフォリオを目指しませんか?
※投資は、お客様自身の判断と責任において行ってください。