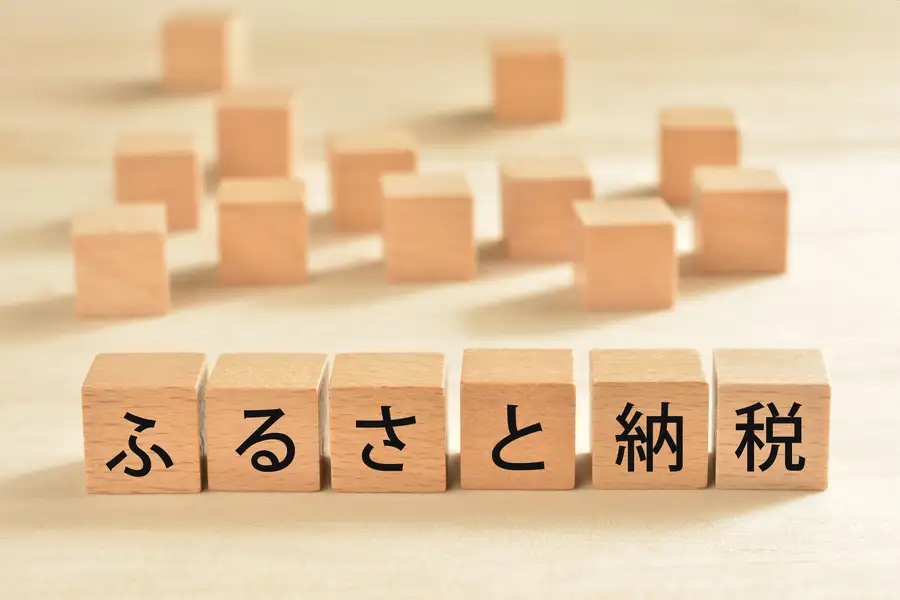投資収支について「これは確定申告が必要なのか?」と疑問に思ったことはありませんか?
本記事では、確定申告が求められる場面や、申告をしなかった場合のリスク、さらに間違えた場合の対処法を詳しく解説します。
投資をするうえで切り離せない税務の問題を把握し、安定的に資産運用を継続するためのポイントを押さえていきましょう。
投資で確定申告をしないと何が起こるのか?
投資で利益が発生しているのにもかかわらず確定申告をしなかった場合、税務署からの指摘や罰則、追徴課税といった経済的負担が生じる可能性があります。
税務署からの指摘や罰則が発生する
税務署は金融機関などから提供される取引情報を元に、投資家の収益状況を把握しているため、未申告の事実が発覚するリスクは高いです。
その場合、税務署から修正申告や追加納税を求められるだけでなく、延滞税や無申告加算税といったペナルティが科されることもあり、通常の納税額以上の経済的な負担が生じるので注意しましょう。
また故意に申告を避けたと判断された場合、重加算税が適用され、罰則の比率も高くなる懸念も生じます。
・延滞税:納付期限を過ぎた日数に応じて基準金利で加算され、支払いが遅れるほど負担が増える点が特徴です。
・無申告加算税:期限内に申告を行わなかった場合に発生します。納付税額のうち50万円までは10%、それを超える部分には15%が科される点が特徴です。
・重加算税:追加の税負担として、納付すべき税額の35%〜40%相当と他の罰金よりも厳しいペナルティとなります。
ペナルティを未然に防ぐために、適切な対応を心がけましょう。
信用情報に影響が出る
未申告が発覚した場合や滞納が続いた場合においては、信用情報が毀損されるリスクを認識しておく必要があります。
未申告や滞納が発覚すると税務調査が行われ、追徴課税や延滞税が発生します。
また滞納が長期化すると財産差押えに至るケースもあり、社会的信用の低下を招く恐れがあります。
特に自営業者やフリーランスの場合、税務上の問題が取引先や顧客の信頼に影響するリスクが高いです。信頼を損なうことで、契約やビジネスの継続に支障をきたすことも考えられます。
投資で確定申告が必要なケースは?
| 区分 | 具体的なケース | 詳細ポイント |
| 必要なケース | 給与所得者で年収2,000万円超 | 給与収入が2,000万円を超える場合、年末調整は対象外であるため、確定申告が必要です。 |
| 副業所得が20万円超 (給与収入を除く) | 給与所得以外に副業収入や不動産収入があり、その所得が年間20万円を超える場合。 | |
| 複数の給与を受けている場合 | 2ヶ所以上から給与を受けており、主たる給与“以外”の給与収入の合計が20万超の場合。 | |
| 株式投資信託を運用している場合 | 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合。 | |
| 不要なケース | 給与所得者で1ヶ所からの給与のみ | 年収2,000万円以下で、給与所得のみの場合、年末調整で対応可能なので確定申告は不要です。 |
| 副業収入が20万円以下 | 副業やアルバイトなどの所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要です(ただし住民税の申告は必要な場合があります)。 | |
| 年金収入が400万円以下かつ 他の所得なし | 公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得がない場合は不要です。 | |
| 行った方が 得するケース | 医療費控除を受けられる場合 | 家族全体の医療費が10万円を超えた場合、所得税が還付される可能性があるため、申告を行うと得をします。 |
| ふるさと納税を利用している場合 | ふるさと納税額が自己負担額(2,000円)を超えた場合、確定申告で還付控除を受けられるため得になります。 | |
| 住宅ローン控除の初年度 | 住宅ローン控除により大幅な税額控除が受けられる可能性があり、所得税の還付が期待できます。 | |
| 雑損控除や寄付金控除が 該当する場合 | 災害や寄付金控除の対象になった場合、申告を行うことで税金が減額または還付されます。 | |
| 配当金がある場合 (総合課税が有利な場合) | 配当金を受け取った場合、総合課税で申告することで税率が低くなる可能性があるため、申告すると有利になる場合があります。 | |
| 株式投資信託の損益通算 | 株式や投資信託の損失を翌年以降に繰り越すことで損益通算可能です。 | |
| 扶養控除の修正が必要な場合 | 年末調整で反映されなかった配偶者控除や扶養控除を追加することで税金が戻る場合があります。 |
投資をしていると、それぞれの投資において確定申告が必要なケースか否か、わかりにくいと感じることもあるでしょう。ここからは、株式投資、FX、不動産投資などそれぞれの投資における確定申告が必要となる条件について、詳しく解説します。
株式投資の場合
株式投資では、取引の種類や利益・損失の状況によって、確定申告が必要になる場合があります。以下に主なケースでの確定申告の必要性をまとめました。
利益が発生した場合
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で取引を行い、1年間の売却益が20万円を超えた場合は確定申告が必要です。一方、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、税金があらかじめ天引きされるため、通常は申告不要です。
損失が発生した場合
売却損が出た場合、翌年以降の利益と相殺できる「繰越控除」や、他の投資収益と損益通算を行うために確定申告をする必要があります。
給与所得者の場合
年間給与が2,000万円以下で、株式投資による利益が20万円以下であれば申告は不要です。ただし複数の証券口座を利用していて、損益通算を行いたい場合は確定申告が必要になる点に注意してください。
FX投資の場合
FX投資では、利益の大きさや状況に応じて確定申告が必要となる場合があります。
FX所得が年間20万円を超える場合
給与所得者であっても、FX取引による利益から必要経費を差し引いた後の所得が20万円を超える場合、申告義務が発生します。
損失が発生した場合
FXで損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除を活用するためには確定申告が必要ですが、将来の利益と相殺して税負担を軽減できる可能性もあります。
不動産投資の場合
不動産投資による利益は、不動産所得に分類されます。不動産所得とは土地や建物などを賃貸することで得られる収入から、必要経費を差し引いたものを指します。以下に、不動産投資で確定申告が必要となるケースを詳しく解説します。また不動産の売買による利益(キャピタルゲイン)に関しては「譲渡所得」として、分離課税の対象となります。
なお、REITは金融商品としてみなされ、配当収益は「配当所得」、売買収益はキャピタルゲインとして「譲渡所得」となり、分離課税の対象となります。
不動産所得が20万円を超える場合
不動産投資で得た収入から必要経費を差し引いた後の所得が年間20万円を超える場合、確定申告が必要です。必要経費には、物件の管理費やローンの利息、修繕費などが含まれます。
不動産投資で赤字が出た場合
赤字の場合でも、他の所得(給与所得など)と損益通算を行うことで、払い過ぎた税金が還付される可能性があります。このため、赤字であっても確定申告を行うことが推奨されます。
確定申告の種類
不動産投資では、青色申告と白色申告のどちらかを選ぶことができます。青色申告は複式簿記による帳簿作成が必要ですが、最大65万円の特別控除を受けられる点がメリットです。
白色申告は単式簿記で簡単に申告できますが、特別控除は適用されません。
不動産投資での収益は、所得税だけでなく住民税にも影響するため、正確に申告することが重要です。また、損失が出た場合も翌年以降の税負担を軽減できる可能性があるため、必要に応じて申告しましょう。
期限内に確定申告を済ませるステップ
確定申告は期限内に正確に行うことが大切です。ここからは、必要書類の準備から申告書の作成、提出方法までの具体的なステップを詳しく解説します。
1.確定申告の準備に必要な書類を揃える
確定申告をスムーズに進めるために、必要な書類を事前に揃えておきましょう。
- 源泉徴収票(給与所得者の場合)
- 収入を証明する書類(個人事業主なら帳簿や請求書など)
- 控除に関する証明書(医療費控除や生命保険料控除など)
- 社会保険料控除証明書
- 寄附金の領収書(ふるさと納税を利用した場合)
- マイナンバーカードのコピー(表裏)
2.申告書を作成する
書類が揃ったら、確定申告書を作成します。確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使ってオンラインで簡単に作成できます。以下は、申告書作成の主な流れです。
- データ入力:収入金額や所得控除など、必要な情報を入力します。入力画面はガイド付きでわかりやすく、初心者でも安心です。
- 計算結果の確認:入力が完了すると、税額の計算結果が表示されます。この時点で還付金や納付金額を確認できるので、振込口座や納付方法を選びましょう。
税務署への提出方法については次で詳しく解説します。
3.申告書を税務署へ提出する
作成した申告書は、以下の方法で提出します。自分に合った方法を選びましょう。
e-Tax(電子申告)
インターネットを使って申告書を送信します。電子署名を行えば、税務署への訪問が不要になり、24時間いつでも手続きが可能です。
郵送での提出
必要書類を税務署に郵送します。消印日が提出日として認められるため、提出期限内に余裕を持って手続きを進めましょう。
窓口での提出
税務署に直接持参する方法です。不備がないかその場で確認してもらえるため、確実に提出したい方に向いています。
どの方法で送付するとしても、期限内に確定申告を終えることが重要です。自分に合った方法を選び、確実に申告しましょう。
確定申告をしなかった・間違えていた場合の対処法
確定申告を期限までに行わなかった場合や内容に誤りがあった場合には、早めの対応が重要です。ここからは、期限後申告の手続き方法や、修正申告、さらに税務署への相談について詳しく解説します。
期限後申告を行う
確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く「期限後申告」を行うことが大切です。期限後申告の手続きは通常の確定申告と同じですが、いくつか注意点があります。
期限後申告の手順
- 通常の確定申告書を作成し、「期限後申告」と明記します。
- 書類を税務署に直接持参するか、郵送またはe-Taxで提出します。
- 納税が必要な場合は、申告書の提出日が納付期限です。
期限後申告では、無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されることがあります。これらのペナルティは申告が遅れるほど増加するため、できるだけ早く対応しましょう。
間違いがあった場合は修正申告を行う
確定申告の内容に誤りがあった場合、「修正申告」を行うことで正しい申告に修正できます。修正申告は、間違いに気付いた時点で早めに対応することが重要です。
修正申告の手順
- 確定申告書第一表と第二表を再度準備し、修正内容を記入します。第一表には「修正申告」と明記し、修正後の正しい金額を記載します。
- 特例適用条文欄に具体的な修正理由を簡潔に記入します。
- 修正申告書は税務署へ直接持参や郵送、e-Taxなどで提出してください。
修正後に税額が増える場合は、修正申告書の提出と同時に追加の税金を納付します。納付が遅れると延滞税が加算されるため、迅速に対応しましょう。
一方、正しい内容を修正申告することで、還付を受けられる可能性もあります。確定申告で間違えていた場合も慌てず、正しく修正申告を行いましょう。
わかりづらいことは税務署に相談する
確定申告の手続きでわからないことがある場合は、税務署に相談してみることもおすすめです。アドバイスを受けることで、申告のミスや手続きの遅れを防げます。
税務署に相談する方法として直接訪問するほか、電話相談や特別相談会を利用することもできるので、自分に適した方法を選びましょう。
また国税庁のウェブサイトには、チャットボット「ふたば」や、よくある質問をまとめた「タックスアンサー」などのオンラインサービスがあります。これらを活用することで、簡単な疑問は自分でも解決できるのでおすすめです。
ご参考:
ふたば( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm )
タックスアンサー( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm )
不明点をそのままにして申告を進めると、後から修正や追加納税が課される場合があります。わからないことがあれば早めに税務署に相談し、正確な申告を心がけましょう。
投資で確定申告が必要かは場合による!しっかり確認を
本記事では、投資における確定申告の必要性や手続き方法について解説しました。申告が必要かどうかは、取引の種類や収益状況によって異なりますが、未申告や間違いがあれば早めに対応することが大切です。 もし、確定申告についてわからないことがあれば、税務署やオンラインサービスを活用して確実に手続きしてください。