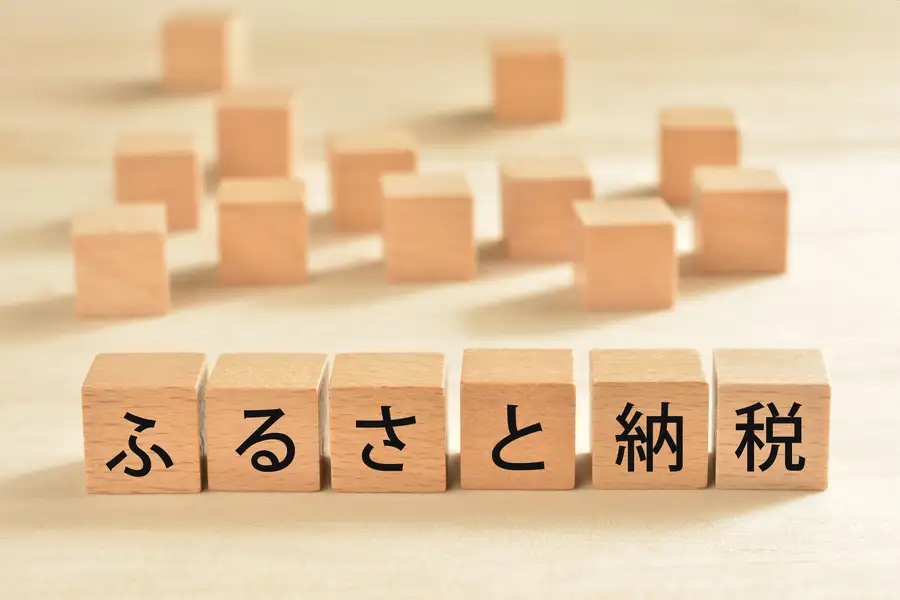「老後2,000万円問題」という言葉に不安を感じる方は少なくありません。ですが、自分が実際にどのくらい年金を受け取れるのか、そして生活費に対してどの程度不足するのかを正確に把握している人は必ずしも多くありません。
年金不足への不安を解消するためには、まず現実を正確に知ることが第一歩となります。ここからは、あなたご自身の年金受給見込額と実際の不足額を具体的に計算していきましょう。
あなたの年金、実際いくらもらえる?
日本の年金制度の基本構造
日本の公的年金制度は「2階建て構造」と呼ばれます。1階部分は、全国民が加入対象の国民年金(老齢基礎年金)で、2025年度の満額は月額6万9,308円となっています(1956年4月2日以降生まれの場合。生年月日により若干の差が生じる場合があります)。2階部分は、会社員や公務員が対象の厚生年金(老齢厚生年金)です。受給額は、現役時代の給与水準と加入期間に応じて決まり、国民年金のみの自営業者などとは水準が大きく異なります。
年金の被保険者は、自営業者や学生などが加入する「第1号被保険者」、会社員や公務員で厚生年金にも加入する「第2号被保険者」、そして第2号被保険者に扶養される配偶者で保険料負担がなく基礎年金を受け取れる「第3号被保険者」の3つに区分されます。
職業・年収別の年金受給額シミュレーション
国民年金のみに加入している場合、現時点では、40年間満額を納めた場合に受け取れるのは月額6万9,308円、年額にして約83万円です。納付期間が短くなればその分減額され、例えば、30年間の納付ではおよそ満額の75%の水準で月額5万1,981円、年額約62万円ほどになります。
一方で、厚生年金も受け取ることができる場合には、受け取れる年金額はその分多くなります。厚生年金は、生涯の平均年収や加入期間によって額が変わりますが、40年間加入した場合の目安として、生涯平均年収が300万円であれば月額約12万7,000円、400万円では約14万4,000円、500万円では約15万9,000円程度になります。
なお、これらはあくまで標準的なモデルであり、実際の年金受給額は、加入期間や保険料の納付状況、繰上げ・繰下げ受給の選択などによって変わってきます。将来の受給見込み額をより正確に知るには、日本年金機構の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用して確認すると良いでしょう。
老後の生活費との比較:不足額を算出すると
では、こうして受け取れる年金収入だけですと、実際の老後生活でどの程度の不足が出るのかについて考えてみましょう。総務省の家計調査報告によれば、65歳以上の世帯の消費支出は、夫婦無職世帯で月額25万6,521円、単身無職世帯で月額14万9,286円となっています(2024年の平均)。例えば、生涯平均年収が400万円の会社員夫婦の場合、夫の年金はおよそ14万4,000円、妻が専業主婦であれば基礎年金の6万9,000円が加わり、合計で月額約20万2,000円となります。生活費との差額は月額約4万7,000円、年間ではおよそ56万円の不足です。自営業夫婦では、夫婦ともに基礎年金のみで合計13万8,000円となり、毎月約11万1,000円、年間にして約133万円の不足となります。
単身の場合は差が小さくなりますが、それでも生涯平均年収400万円の元会社員で月額約1万円、元自営業者では月額約7万4,000円の不足となります。これらはあくまで平均的な生活費に基づく試算であり、趣味や旅行、さらには医療や介護の出費を考慮すると、必要な資金はさらに膨らむことになります。
ちなみに、「老後2,000万円問題」の契機となった金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」(2019.6.3 金融庁)では、高齢夫婦無職世帯の収入から支出を引いた月平均不足額が約5万円で、20年で約1,300万円、30年で約2,000万円の金融資産取り崩しが必要になると試算されています。
投資で年金不足を補う方法

多くの世帯は年金だけで老後の生活費をまかなうことは難しいのが現実です。その不足を補うためには、現役時代から計画的に資産形成を進めることが欠かせません。
ここでは、まず資産形成に役立つ制度「 iDeCo」と「NISA」について確認しておきましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、公的年金に上乗せして老後資金を形成するための私的年金制度です。拠出時、運用時、受取時のいずれにおいても税制上の優遇を受けられる点が特徴です。拠出した掛金は全額が所得控除の対象となり、例えば年収400万円の会社員が月2万円を拠出すると、年間24万円の所得控除を受けることができ、所得税・住民税の負担が軽減されます。運用益についても非課税で、受取時には退職所得控除や公的年金等控除の対象となります。
今年6月に成立した年金制度改正法では、3年以内にiDeCoの拠出限度額の引き上げが実施されることになっています。現行制度では、自営業者は月額6万8,000円、会社員(企業年金なし)は2万3,000円まで拠出可能ですが、改正後はそれぞれ7万5,000円、6万2,000円へと拡大される見通しです。これにより、非課税で運用できる金額が増え、老後資金形成の選択肢が広がることになります。
一方で、iDeCoは、60歳から資産を受け取ることができるのですが、それまでは原則として引き出すことができない仕組みである点には留意が必要です。長期的な資産形成に適した制度であり、老後資金を準備する方法のひとつとして検討する価値があります。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは、「少額投資非課税制度」のことで、個人の資産形成を支援するための国の税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などの金融商品で利益(売却益や配当金など)を得ると、その利益に対して20.315%の税金(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)がかかります。しかし、NISA口座で投資した場合は、この税金がかからず、運用で得た利益を非課税で受け取ることができます。
2024年、このNISA制度の全面的見直しが実施され、より使いやすくなりました。最大の特徴は「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つを同時に使えるようになったことで、成長投資枠240万円とつみたて投資枠120万円、年間合計で最大360万円の投資枠が与えられています。
また、非課税保有限度額は、成長投資枠が1,200万円、つみたて投資枠が成長投資枠との合計で1,800万円となりました。加えて、一度得た非課税メリットは恒久化され、保有期間の制限もなくなりました。
この改正を受け、利用者の間では「成長投資枠」「つみたて投資枠」両方を活用するケースが増えています。日本全体でも「預貯金から投資へ」という流れが進む中、NISAは大きな役割を果たすものといえるでしょう。
iDeCoとNISAの使い分けとしては、iDeCoが「節税重視」で60歳まで資金の引き出しができないのに対して、NISAは「引き出し自由」で流動性が高い点が対照的です。理想的には、iDeCoで老後資金の基盤を築きつつ、余裕資金をNISAで運用するという組み合わせが効果的です。
投資対象の選び方

前章では、老後資金を準備するために利用できる制度について整理しました。それでは実際に資産を運用する際、どのような考え方で投資対象を選べばよいのでしょうか。ここでは、分散投資の基本から具体的な資産の役割、そして運用方法についても見ていきます。
分散投資の重要性
投資を始める際にまず大切なのは分散投資です。ひとつの商品や資産に偏ると、相場が下落したときに大きな損失を抱えるリスクがあります。株式、債券、金(ゴールド)など、性質の異なる資産に分けて投資することで、一方が下がっても他方が下支えする仕組みをつくれます。特に長期で資産形成を考える若い世代にとって、リスクを抑えながら成長の果実を取り込むための基本戦略が分散投資です。
投資の選択肢:株式・債券・金・保険・不動産
投資の選択肢として代表的なものについて、それぞれの特徴を見ておきましょう。
「株式」は、経済の成長を取り込める資産で、長期では右肩上がりのリターンが期待できます。インデックスファンドを通じて世界中の株式に投資すれば、個別企業の値動きに左右されにくく、安定的な成長を狙えます。業績や配当水準に眼を向けて個別株式を検討される方もいらっしゃることでしょう。ただし、株式は元本割れのリスクがあることを忘れてはなりません。
「債券」は、株式よりも値動きが小さく、安定的な利息収入が得られる資産です。市場金利が上昇すると債券の価格は下がるものの、満期まで保有すれば利息・元本を確実に受け取れる点で、投資の安定感を高めます。ただし、債券発行体の信用リスクには留意が必要です。
「金(ゴールド)」は、株や債券と異なる動きをするため「守りの資産」と呼ばれています。インフレや地政学リスクが高まる局面でも価値を保ちやすく、資産の一部を金に振り分けることで想定外の事態への備えとなります。
「個人年金保険」は、老後資金の積立てを主な目的とする任意の保険で、元本保証を重視する人に適しており、契約時点で受取額が確定している安心感があります。さらに生命保険料控除の対象にもなるため、税制面でのメリットもあります。
「不動産投資」は、まとまった資金があり余裕のある方にとって選択肢のひとつとなります。不動産投資は家賃収入という安定的な収益が得られる一方で、初期投資が大きく、物件管理の負担も伴います。代替策として、少額から始められる不動産投資信託(REIT)に投資する手もあります。
コア・サテライト戦略で無理なく投資
初心者におすすめなのが「コア・サテライト戦略」です。資産運用のコア(土台)には、債券に加えて日経平均連動ファンドあるいは全世界株式や先進国株式などのインデックスファンドを積立投資し、着実に長期の成長を取り込みます。その上で、サテライト(衛星)としてテーマ型の投資信託や個別株式、金などを少額で組み合わせます。
この手法であればコア部分で安定した資産形成を進めつつ、サテライト投資で投資の幅を広げられるため、リスクを抑えながら楽しみを持って運用を続けられます。20〜30代のように運用期間が長く取れる世代には特に有効なアプローチです。
投資以外の対策

投資で不足分を補うだけでなく、実は公的年金制度そのものにも受給額を増やすための仕組みが存在します。なかでも注目すべきは、受給開始時期を調整することで年金額を増やす繰下げ受給です。また、持ち家の資産価値を活用して収入を得る方法もあります。
年金の繰下げ受給
「年金の繰下げ受給」とは、本来65歳から受け取れる年金の開始時期を遅らせ、その分受給額を上乗せする制度です。1か月繰り下げるごとに0.7%増額され、この増額は生涯にわたって続きます。2022年4月の制度改正により、繰下げ可能年齢は従来の70歳から75歳へ延長されました。これにより最大で120か月(10年)遅らせることができ、増額率は最大84%に達します。
たとえば、65歳から月15万円の厚生年金を受給予定の人が、70歳まで繰り下げた場合、42%増額されて月額は約21万3,000円になります。さらに75歳まで繰り下げれば、84%増額の約27万6,000円に達します。年間ベースで見ると、65歳開始の180万円に対し、70歳開始では約255万6,000円、75歳開始では約331万2,000円と、受給額に大きな差が生じます。
ただし、加給年金(配偶者加給年金:配偶者が65歳になるまで年額23万9,000円、など)は繰下げ増額の対象外です。また、年金額が増えることで税金や介護保険料、国民健康保険料などの負担が増す可能性もあります。
65歳以降も働き続ける場合には、在職老齢年金制度といって、一定額以上の報酬があると年金額が減額されることとなり、繰下げの効果が薄れる可能性もあります。さらに、繰下げ期間中に亡くなった場合、その間の年金は受け取れなくなるため、ご自身の健康状態や平均余命を踏まえて総合的に判断を下すことが重要です。
以上が年金の繰下げ受給についてですが、ここで繰上げ受給についても触れておきましょう。年金は、受給開始を65歳より早める繰上げ受給も可能です。こちらは1か月早めるごとに0.4%減額され、この減額率は一生涯続きます。60歳から受け取る場合は、65歳開始よりも24%減額されます。例えば、65歳から月15万円を受け取れる人が60歳で繰上げ受給する場合、月額は約11万4,000円に減ります。また、繰上げ受給を選択すると、障害基礎年金や遺族年金の受給資格が制限される場合があります。そのため、ご自身のライフプランや健康状態、就労の有無などを総合的に考慮して選択することが大切です。
持ち家を活用した資金調達
持ち家がある場合、その資産価値を活かして現金化する方法が、「リースバック」と「リバースモーゲージ」です。特に高齢期は引っ越しの負担や住環境の変化が大きいため、ご家族やお子さまの了承が得られるのであれば、住み慣れた家に住み続けながら資金を得られる仕組みは有効な選択肢といえます。
「リースバック」は、自宅を不動産会社などに売却し、そのまま賃貸契約を結んで住み続ける仕組みです。売却代金を一括で受け取れるため、まとまった資金を確保でき、固定資産税や修繕費の負担もなくなります。ただし、新たに家賃の支払いが発生し、所有権を失うことで相続に影響する点には注意が必要です。
「リバースモーゲージ」は、自宅を担保に金融機関や自治体から融資を受ける制度です。契約者が生存中は返済不要で、死亡後に不動産を売却して返済します。所有権を維持したまま資金を得られる利点がありますが、リースバックと同様に相続に影響しますし、不動産価格の下落や金利上昇によって想定以上の返済負担が発生するリスクがあります。
まとめ
ここまで、年金不足を解消するためのさまざまな方法を見てきました。まず大切なのは、漠然と不安を抱えるだけでなく、まず自分の状況を正確に把握することです。そのうえで、iDeCoやNISAを活用した資産形成を含めて複数の手段を組み合わせることで、安定した老後資金の確保が可能になります。
これらの対策は、始める時期が早いほど効果が大きくなります。特に資産運用は複利の力によって、長期になるほど成果が積み上がります。老後の安心は、待っていても訪れません。今この瞬間から計画を立て、小さくても第一歩を踏み出すことが、将来の大きな安心につながります。
※投資は、お客様自身の判断と責任において行ってください。