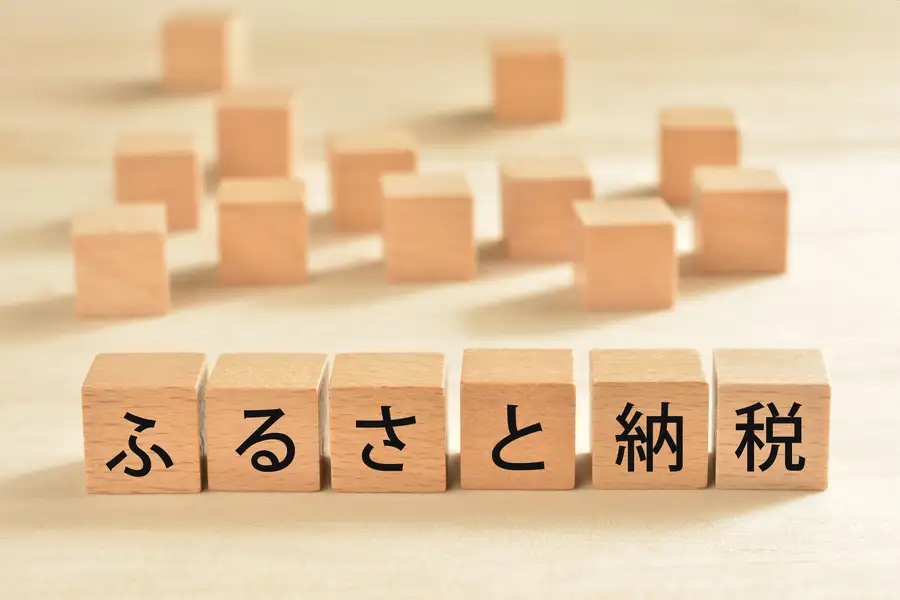「退職金をもらったけれど、どう運用すればいいかわからない」「銀行に預けているだけでは老後が不安」そのような思いを抱えていませんか?
人生100年時代と言われる今、退職金はいくらになるのか、退職金の使い道をどうしようか、思案されている方もいらっしゃることでしょう。本記事では、退職金を運用する場合の基本、具体的な始め方、さらには様々な運用方法の比較まで、初心者の方でも安心して退職金運用を始められるよう、ご紹介していきます。
ぜひ最後までお読みいただき、あなたの豊かな老後生活の実現のために、退職金運用の第一歩を踏み出す一助となればと思います。
退職金運用の仕組みと初心者が知るべき投資の基本
ライフプランで考えよう、退職金の使い道
退職金運用とは、受け取った退職金を活用するために金融商品に投資することを指します。
しかしながら、現実的には退職金の全額を直ちに運用に回せる訳ではありません。多くの方が直面するのは「退職金をどのように配分するべきか?」という課題です。
退職金を受け取った際に考慮すべき主な使い道として、まず住宅ローン等の借入の完済に向けた行動をとることが挙げられます。例えば、借入金利1.5%の住宅ローンが残っている場合、その金利以上のリターンを安定して得ることは必ずしも容易ではありません。運用以前に借入金の返済を優先することは、経済的合理性のある判断といえます。
次に重要なのが生活費に向けた資金の確保です。総務省による2024年の家計調査によると夫婦高齢無職世帯(65歳以上の夫婦のみの無職世帯)の可処分所得は月間約22万円、消費支出は26万円弱とされています。普段の生活に加えて、趣味、娯楽、旅行などに使いたいお金もあることでしょう。当面の不足分を補う手許資金として、いつでも引き出せる預貯金に100万円から200万円程度を置いておく必要もあります。
予期せぬ出費への備えも欠かせません。住宅のリフォーム費用、お子さんの結婚への備え、親の介護費用、ご自身の老後の医療費や家族の緊急事態への備えなど、一生の中では様々な出費が発生する可能性があります。これらに備えて、生活費とは別に緊急時のための資金として預貯金あるいは換金しやすい金融商品で200万円から500万円を用意しておくと安心です。
退職金運用を始める時に何を検討する?
退職金運用をしようとする場合、「いくらまで資産を増やしたいか」という明確な目標設定があると良いでしょう。目安として、例えば、1,000万円の退職金を10年で1,500万円に増やすのであれば年間4.1%のリターンでの複利運用、20年間で1,500万円に増やすのであれば年間約2.1%のリターンでの複利運用を行う必要があります。同様に20年間で2,000万円にする場合には年間約3.6%のリターンが求められます。
現実的な運用の目標収益率と金融商品の選択肢として、以下の水準が参考になります。
保守的な運用 :年1%~3% → 主に債券や定期預金中心の運用
バランス型運用 :年3%~5% → 株式と債券を組み合わせた分散投資
やや積極的な運用:年5%~7% → 株式中心のポートフォリオ(リスクも高い)
退職金運用で資産を増やすには長期の運用が望まれます。長期運用には短期的な市場変動に左右されにくく、安定した資産形成が期待できるメリットもあります。
一方で、リターンは再投資せず、毎月の生活費やレジャーに使うという方もいらっしゃるかも知れません。その場合には運用資産を増やすことは難しくなります。ただし、その場合にも、年間の目標収益率の水準、つまり、どの金融商品で運用するか?については考えておく必要があります。
退職金運用における投資商品の種類と特徴
退職金の運用可能額が決まったら、次に具体的な投資商品を検討します。
商品選択に際しては、投資の基本原則である「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」の関係を理解することが重要です。
元本保証型商品から見ていきましょう。銀行の「定期預金」の金利は現在年0.25%から0.50%程度となっています。住宅ローンを完済して退職金運用の安全性を重視したい場合には、有効な選択肢となります。特に、生活費や緊急資金への備えとしては、元本の安全性を最優先に考えた定期預金や個人向け国債での運用が適しています。
投資型商品については、「投資信託」のバランス型商品であれば年3%から5%程度のリターンが期待でき、長期的な資産増加が期待できます。しかしながら、時には値下がりする市場リスクを伴うことに留意しなければなりません。高配当株のETFや日経平均に連動する投資信託であれば個別銘柄株のリスクを軽減しつつ株式市場の動向を取り入れる恩恵を受けることができます。
個別株への「株式投資」では配当利回りが年4%程度の銘柄もありますし、株価の値上がり(キャピタル・ゲイン)も期待できますが、反面、値下がりすることもある、株価変動リスクに留意しなければなりません。そのリスクを取る価値があるかをご自身で慎重に判断しましょう。
「不動産投資信託(REIT)」も退職金運用の選択肢として考えられます。分配金利回りが年3%から4%程度の商品が多く、定期的な収入源として魅力的です。ただし、不動産価格の変動リスクもあるため、運用資金の一部に限定して投資すると良いでしょう。
ここで一言、投資まがいの詐欺にはくれぐれもご注意してください。「年15%の高利回りで元本保証」といった話は、金融の常識から考えてありえません。また、「事業への投資で高配当」「未公開株への投資」「海外の不動産事業への参加」といった事業投資の話も要注意です。これらの投資案件は専門的な知識と経験が必要な分野で、よほどのことがない限り、個人が退職金のような大金を投じるものではありません。
退職金運用で活用したいNISA制度
投資型商品を選択する際に、ぜひ活用していただきたいのがNISA(少額投資非課税制度)です。
通常、株式や投資信託などの金融商品の場合、売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISAを利用した場合には、金融商品から得られる利益が非課税となります。同じ100万円の利益でも、NISA口座であれば税金を引かれることなく満額を受け取ることができますので、長期運用においては大きな差となってきます。
ただし、NISA口座には投資できる上限金額があります。2024年からの新NISA制度では、年間投資枠が360万円(つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円)、生涯投資枠が1,800万円となっています。退職金運用においては、この非課税枠を最大限活用することで、運用効率を大幅に向上させることができます。
退職金運用で重要な3つの基本原則
ここで、退職金運用を成功させるための3つの基本原則をご紹介しておきましょう。
第1の原則は、「適切な資金配分と優先順位の設定」です。
退職金は全額を運用に回すのではなく、まず高金利の債務がある場合はその完済を最優先とします。
はじめにもご説明しましたが、住宅ローンの金利が年1.5%であれば、この金利を確実に削減できる効果は、投資のリターンと同等の価値があります。次に、生活費と緊急資金を確保し、最後に余剰資金での運用を検討するという順序が重要です。
運用資金内での分散投資も重要な要素です。運用可能資金が500万円ある場合、国内外の株式、債券、不動産など複数の資産クラスに分散して投資することでリスクを軽減できます。
一般的には、年齢に応じて「100マイナス年齢」の考え方を適用し、60歳であれば株式40%、債券50%、現金10%といった配分が推奨されるといわれています。
第2の原則は、「長期投資の継続」です。
退職金は老後の長期間にわたって活用する資産であるため、短期的な市場変動に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で運用することが重要です。過去のデータを見ると、株式市場は10年~20年といった長期間では相当な株価上昇となっています。また、他の金融商品であっても複利効果を活用することで、時間を味方につけた資産成長が期待できます。
第3の原則は、「定期的な見直しと生活状況の変化への対応」です。
投資をしたからOKといって放置するのではなく、年1回はポートフォリオの見直しをしましょう。市場環境の変化だけでなく、自身の健康状態、家族構成、住居状況の変化に応じて、投資配分を調整することが大切です。
この3つの基本原則を守ることで、現実的な制約の中でも、退職金を効果的に運用し、安定した老後生活の基盤を築くことができるでしょう。
退職金運用の具体的な始め方4ステップ

ステップ1:運用目標と期間の設定
退職金運用を始める前に、ご自身のライフプラン、年ごとの収支計画をよく検討したうえで、そのプランに寄り添った明確な運用目標と期間を設定することが重要です。運用目標の設定においては、具体的な金額目標と期間を明確にする必要があります。例えば、「20年間で退職金1,000万円を1,500万円に増やす」といった具体的な目標を設定しましょう。
運用期間の考え方も重要です。60歳で退職金を受け取った場合、後期高齢者となる75歳までと仮定すると15年間の運用期間があります。ただし、この全期間を積極的な投資に充てるのではなく、段階的にリスクを下げていく戦略が一般的です。60歳から70歳までの10年間は比較的積極的な運用を行い、70歳以降は安全性を重視した運用に切り替えるといったアプローチが考えられます。
また、運用目標を設定する際には、インフレ率も考慮する必要があります。日本の過去20年間の平均インフレ率は年0.7%程度ですが、今後は1%から2%程度のインフレが見込まれています。このため、実質的な資産価値を維持するためには、最低でもインフレ率以上のリターンを確保する必要があります。
ステップ2:リスク許容度の診断と投資方針の決定
運用目標が決まったら、次に自分のリスク許容度(投資によって損失が発生した場合に、どの程度まで受け入れることができるか)を把握し、それに基づいた投資方針を決定する必要があります。
リスク許容度の診断では、まず経済的な余裕度を確認します。
退職金以外の資産状況、年金受給額、配偶者の収入や資産などを総合的に評価し、投資に充てることができる金額を決定します。
また、心理的なリスク許容度も重要な要素です。
投資経験の有無、金融商品に対する理解度、市場の変動に対する耐性などを自己評価する必要があります。投資未経験者の場合は、まず小額から始めて徐々に投資額を増やしていく段階的なアプローチが適しているでしょう。
さらに、年齢と健康状態もリスク許容度に大きく影響します。
60歳で退職金を受け取る場合と、65歳で受け取る場合では、運用期間が5年間の違いがあるため、取れるリスクも変わってきます。また、健康状態が良好であれば長期運用も可能ですが、健康不安がある場合は、より安全性を重視した運用方針を選択する必要があります。
これらの診断結果を基に、具体的な投資方針を決定します。
保守的な投資方針では、債券や定期預金の比率を高めに設定し、年2%から3%程度のリターンを目指します。
バランス型の投資方針では、株式と債券を半々程度に配分し、年3%から5%のリターンを狙います。
積極的な投資方針では、株式の比率を高めに設定し、年5%以上のリターンを目指しますが、その分リスクも高くなります。
ステップ3:具体的な投資商品の選定
投資方針が決まったら、具体的な投資商品を選定します。退職金運用では、複数の商品を組み合わせることで、リスクの分散と安定したリターンの確保を目指します。
債券
債券部分については、個人向け国債や社債、債券型投資信託を活用します。
個人向け国債は元本保証があり安全性が高い一方、利回りは低めです。社債は国債より利回りが高い傾向がありますが、発行企業の信用リスクを考慮する必要があります。債券型投資信託では、複数の債券に分散投資することでリスクを軽減できます。
株式
株式部分については、個別株投資、株式型投資信託、ETFなどの選択肢があります。
退職金運用では、個別株よりも分散効果の高い投資信託やETFを活用することが一般的です。国内株式だけでなく、先進国株式や新興国株式への投資を含めることで、地理的な分散効果も期待できます。
投資信託
投資信託を選ぶ際には、運用コストも重要な要素です。信託報酬が年1%を超える商品は避け、できれば年0.5%以下の低コスト商品を選ぶことで、長期運用における収益性を向上させることができます。また、運用会社の実績や運用方針も確認し、安定した運用が期待できる商品を選定しましょう。
ステップ4:運用開始後のメンテナンス方法
投資を開始した後も、定期的なメンテナンスが重要です。適切なメンテナンスを行うことで、運用成果を向上させ、目標達成の確率を高めることができます。
まず、定期的なポートフォリオの確認を行います。月1回程度の頻度で、各資産の評価額や配分比率を確認し、大きな変動がないかをチェックしましょう。チェックした各項目、即ち、評価額、各商品の運用成績、配当や分配金の受取額などについて記録し、運用目標に対する進捗状況を把握しておくことも重要です。
市場の変動により、当初の投資配分から大きく乖離している場合は、リバランスを検討する必要があります。リバランスとは、意図する配分からずれた時に修正する操作のことで、利益確定と損失抑制の両方の効果が期待できます。
例えば、株式50%:債券50%の配分で始めたとして、株価上昇により株式60%:債券40%になった時に、リバランスとして株式の一部を売却して債券を購入し、元の配分に戻す操作を行うことになります。
市場環境や自身の状況の変化に応じて、運用方針の見直しも必要です。健康状態の変化、家族構成の変化、介護費用の必要性など、当初想定していなかった状況が発生した場合は、より安全性を重視した運用方針への変更を検討しましょう。
退職金運用の選択肢を徹底比較:あなたに最適な運用方法は?
元本保証型 vs 投資型:それぞれのメリット・デメリット
退職金運用において最も重要な選択の一つが、元本保証型商品と投資型商品のどちらを中心とするかという判断です。それぞれの特徴を詳しく比較し、自分の状況に最適な選択を行いましょう。
元本保証型
元本保証型商品の代表例である定期預金は、最大のメリットとして元本の安全性が挙げられます。預け入れた金額が減ることはなく、確実に元本を保護できるため、心理的な安心感があります。また、預金保険制度により1,000万円までは金融機関が破綻しても保護されるため、制度面での安全性も確保されています。一方で、現在の金利水準が低く、物価上昇に対して実質的な資産価値が目減りするリスクがあります。
投資型
投資型商品の代表格である投資信託は、高いリターンが期待できる一方で、元本割れのリスクがあります。特に株式を中心とした投資信託では、短期的に20%から30%の価格変動が発生することも珍しくありません。しかし、長期間保有することで、この価格変動リスクは軽減される傾向があり、複利効果により資産を大きく成長させる可能性があります。
株式投資は最も高いリターンが期待できる投資型商品ですが、同時に最も高いリスクを伴います。個別企業の業績や市場全体の動向に大きく左右されるため、専門的な知識と経験が必要です。配当利回りの高い銘柄を選ぶことで、安定したインカムゲインを得られる場合もありますが、配当の減額や無配転落のリスクも考慮する必要があります。
実際の資産配分を考える際には、年齢と運用期間を重要な要素として考慮します。60歳時点では「100マイナス年齢」の考え方を適用し、株式の配分を40%程度とし、残りを債券や現金で運用するのが一般的です。年齢が上がるにつれて株式の比率を下げ、より安全性の高い資産に移行していく戦略が推奨されています。
自己運用 vs プロ運用:運用方法の比較
退職金運用のもう一つの重要な選択が、自分で運用するか、プロに任せるかという判断です。それぞれのアプローチには異なるメリットとデメリットがあります。
自己運用
自己運用の最大のメリットは、運用コストの削減です。証券会社の手数料や投資信託の信託報酬を最小限に抑えることで、長期的に見て大きなコスト削減効果が期待できます。
また、自己運用では投資判断を自分でコントロールできるため、市場環境の変化に応じて柔軟に対応することが可能です。自分のリスク許容度や運用目標に完全に合致した投資を行うことができ、納得感のある運用が実現できます。投資に関する知識も向上し、市場動向への理解が深まることで、より効果的な投資判断ができるようになるでしょう。
一方で、自己運用にはデメリットも存在します。投資判断を全て自分で行う必要があるため、相当な時間と労力を要します。市場の調査、銘柄の分析、ポートフォリオの管理など、継続的な学習と作業が必要となります。また、感情的な判断により、適切でない投資行動を取ってしまうリスクもあります。市場が大きく下落した際に狼狽して売却したり、逆に過度に楽観的になって大きなリスクを取ったりする可能性があります。
プロ運用
プロ運用の代表例であるファンドラップや投資顧問サービスでは、専門家が個人の投資目標とリスク許容度に応じて最適なポートフォリオを構築し、継続的に管理を行います。豊富な投資経験と専門知識を活用して、個人では困難な高度な投資戦略を実行することが可能です。また、感情に左右されない客観的な投資判断により、市場の変動に適切に対応できるメリットがあります。
プロ運用のデメリットは、比較的高い運用コストです。ファンドラップサービスでは年1%から2%程度の手数料が一般的で、長期運用において相当なコスト負担となります。また、運用方針や投資判断について、個人の意向が完全に反映されない場合もあります。プロの判断が必ずしも正しいとは限らず、市場環境によっては期待した成果が得られない可能性もあります。
中間型
中間的な選択肢として、ロボアドバイザーサービスも注目されています。AIを活用した自動運用により、低コストでプロレベルの投資管理を受けることができます。手数料は年0.5%から1%程度と比較的低く、24時間いつでも運用状況を確認できる利便性があります。ただし、個別の相談や複雑な要望への対応は限定的で、画一的なサービス内容となる傾向があります。
最適な選択は、個人の投資経験、利用可能時間、コスト許容度によって異なります。投資初心者の場合は、まず低コストのインデックス投資信託で自己運用を始め、徐々に投資知識を蓄積していくアプローチが効果的でしょう。十分な資産があり、高度な運用サービスを求める場合は、プロ運用を検討する価値があります。
【まとめ】退職金運用で豊かな老後を実現するための次のステップ

本記事では、退職金運用の基本的な仕組みから、具体的な始め方、様々な選択肢の比較まで解説してきました。
退職金運用では、まず明確な運用目標と期間を設定することが重要です。自分のリスク許容度を把握し、それに基づいた投資方針を決定してください。分散投資、長期投資、定期的な見直しという3つの基本原則を守ることで、リスクに配慮した安定した資産形成が期待できます。
投資商品の選択においては、元本保証型と投資型のバランスを考え、自分の年齢や状況に応じた資産配分を行うことが重要です。また、自己運用とプロ運用のどちらにするかも、個人の投資経験や利用可能時間を考えて判断しましょう。
定期的なメンテナンスも忘れずに行いましょう。定期的なリバランス、運用状況の記録、市場環境や自身の状況変化に応じた運用方針の見直しを継続することで、長期的な運用成果の向上が期待できます。
正しい知識と適切な戦略で退職金運用を行えば、確実に老後の安心を築くことができます。
この記事で得た知識を活用し、あなたに最適な退職金運用を始めてみてはいかがでしょうか。豊かで安心な老後生活の実現に向けて、今日から第一歩を踏み出しましょう。
※投資は、お客様自身の判断と責任において行ってください。