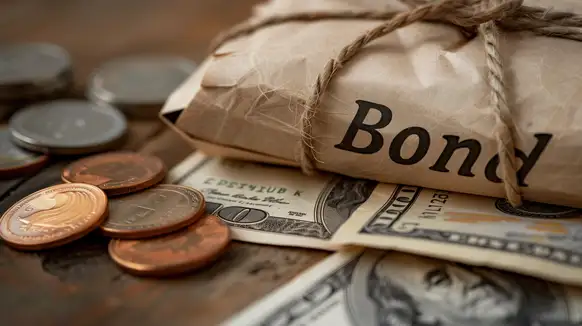「海外ETFに興味があるけど、リスクが心配…」「どんなデメリットがあるの?」このような疑問は多いでしょう。海外ETFは分散投資の有力な選択肢ですが、その特徴とリスクを理解することが成功への第一歩です。本記事では、基本から最新動向、そして初心者が知るべきデメリットと対策を解説します。なお、本記事は、日本に居住する日本国籍のみを保有する方を対象とした記事です。また、海外ETFは米国ETFを対象としております。
海外ETFの基本と最新動向
まずは海外ETFの基礎知識とその動向について押さえておきましょう。
海外ETFの定義と基本的な特徴
海外ETF(Exchange Traded Fund:上場投資信託)とは、海外の取引所に上場している投資信託です。金融庁によれば、ETFとは「特定の指標に連動する投資信託で、取引所に上場し株式同様に売買できる金融商品」とされています。
最大の特徴は、少額から効率的に分散投資ができる点です。例えば、S&P500連動ETF1口で、S&P500という指数を構成する米国主要500社に分散投資した時と同じ効果が得られます。
国内ETFとの主な違い
海外ETFは、国内ETFと比べ銘柄数が豊富で、米国市場だけでも2,000種類以上が存在します。運用コスト面でも、その多くは国内ETFより信託報酬が低く、人気の米国大型株ETFには年率0.03%程度のものもあります。例えば、米国の大手資産運用会社であるVanguardが提供している「Vanguard S&P 500 ETF(VOO)」は、2025年4月11日の時点では年率が0.03%となっています。また海外ETFは国内ETFとは異なり、為替変動の影響を直接受ける点や、税制面での処理が複雑になるため注意を払う必要があることを覚えておきましょう。
規模拡大の歴史と最新トレンド
2025年現在に至るまで、ETF市場は拡大し続けています。1990年3月17日に、カナダ・トロント株価指数に連動する投資信託として世界で初めてETFが誕生して以降、徐々にその規模は拡大し、特に2000年以降は上場銘柄数・規模ともに急拡大してきました。そして2023年12月には、世界の証券取引所には約12,000以上のETFが上場され、純資産残高はおよそ約11兆5,145億米ドル(約1,623兆円)規模にまで拡大しています。近年のトレンドとしては、ETFの中でも特にアクティブ型ETFが急成長を見せています。
東証による流動性向上の新制度
2025年5月7日(水)からETF等の呼値の適正化が実施されることが決まりました。呼値とは売買の注文を行う際の価格の刻み幅のことで、これが適正化されると、同じ資金額の準備でも売買の単位がより柔軟に決められることとなり、投資家にとってより利用しやすくなります。さらにそこに指数連動商品の分散投資効果を加味すると、日本の個人投資家にとっても海外ETFを活用しやすい環境がより一層整うといえるでしょう。
海外ETF投資の主なデメリット

海外ETFは魅力がある一方で、投資を始める前に理解しておくべきデメリットも存在します。特に初心者の方は、これらのリスク要因を事前に把握することで、より賢明な投資判断ができるようになります。
為替リスクとその具体的な影響
海外ETFは、投資対象の価格変動リスクに加え、その海外ETFが上場している市場の通貨で決済されるため、円と外貨の為替変動による影響が大きく、デメリットのひとつとして挙げられます。ですが、為替変動は必ずしも投資家にとって悪影響を及ぼすだけではありません。例えば、米国市場に上場されたETFに投資した場合、ETF自体の価格が10%上昇したとしても為替相場が約定時の価格から「円高ドル安」が進むと値上がり益は目減りしてしまいます。ですが、為替相場が「円安ドル高」に進むと、ETF自体の値上がり益に加え為替差益を得ることも可能です。海外ETF投資にとって、為替変動は単なるデメリットとして敬遠するのではなく、状況に応じた立ち回りを行うことによって武器とすることもできることを覚えておくと良いでしょう。
二重課税問題と税金面でのデメリット
海外ETFを保有する際の大きな課題が「二重課税」問題です。
例えば、米国で配当所得に対して10%が源泉徴収され、その後日本国内において差し引きされた配当所得に対して所得税・住民税(合計20.315%)が課税されることとなります。基本的には、日米租税条約に基づく税額控除によって米国での源泉徴収が10%に軽減されますが、183日を超えて米国内にいるなど、一部の限定的な状況においては最大30%米国で源泉徴収されます。(注)
(注)日本に所在する日本国籍の人が、前年に米国に183日滞在するなど税法上の米国人となった場合を前提に記載しています。
金融庁も海外投資における税制は複雑であり、投資家は専門家への相談を検討すべきであると注意喚起しています。
手数料構造と隠れたコスト分析
海外ETFへの投資では、様々な手数料が発生します。これらは一見小さく見えても、長期的には大きな影響を及ぼします。投資の世界で広く知られている事実として、一般的に海外ETF投資では、売買手数料、為替手数料、保管料などの複数のコストが発生します。海外ETFを売買する際には、国内ETFよりも高い売買手数料(約0.45%前後)がかかり、外貨両替の際の為替手数料(片道0.25%~0.5%程度)も見逃せません。
さらに、ETF自体の信託報酬に加え、海外保管料が別途必要になる場合もあります。基本的には無料の証券会社が多いですが、念を入れてチェックをしたほうが良いでしょう。こうした「隠れたコスト」が投資リターンを侵食する可能性があります。
情報格差と時差による運用上の難点
海外ETFへの投資では、情報面でのハンディキャップも存在します。金融庁も海外市場への投資では、情報の非対称性や言語の壁による情報収集の難しさがあると指摘しています。
米国市場を例にとると、日本との時差は14時間(サマータイム期間は13時間)あり、米国市場が活発に動いている時間帯は日本では夜間から早朝です。そのため、市場の急変時に迅速な対応が難しい場合があります。
また、企業の決算発表やマーケットに影響を与えるニュースも、その多くは英語で発信されるため情報収集と分析で障壁となりかねません。こうした情報格差は無視できないデメリットです。
海外ETFのリスク対策と注意点

海外ETFのデメリットを理解したところで、次はそれらのリスクへの対処法を考えましょう。適切な対策により、メリットを最大化しながらリスク要因を最小化することが可能です。
為替リスクへの具体的な対策方法
為替リスクはいくつかの方法で軽減できます。しかし、為替ヘッジは為替変動リスクを抑える効果もありますが、一方でそのコストが運用成績に影響する場合もあります。まず、投資商品選びの段階で為替変動リスクを回避することが可能な「為替ヘッジあり」のETF商品を選択する方法があります。為替ヘッジ型ETFは為替変動の影響を抑えられますが、円金利と投資先通貨の金利差が大きい場合はコストも大きくなります。
また、投資の鉄則として「長期・分散・積立」の原則に則ることも有効な手立てとなります。特に「ドルコスト平均法」による定期的な積立投資は、為替の一時的な変動に左右されにくくなります。円高時には多くの口数を購入でき、円安時には少ない口数になりますが、平均すれば為替の影響を和らげられます。
税金負担を軽減するための実践テクニック
二重課税問題には、正しい知識と適切な申告が重要です。日本の証券会社で米国ETFを購入する場合、証券会社が「W-8BENフォーム(米国に居住していないことの証明書)」を代行で提出してくれる場合がほとんどで、米国での源泉徴収は通常10%が自動で適用されます。また、確定申告時に「外国税額控除」を適用することで、海外で支払った税金の一部または全額を日本での税額から控除できます。さらに、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの非課税制度を活用する方法もあります。これらを利用すれば日本側での課税を避けられますが、海外での源泉税は課税される点に注意が必要です。
手数料を抑えた効率的な売買・運用方法
手数料負担を軽減するには、効果的な方法があります。
まず、売買回数を抑えることが重要です。頻繁な売買は手数料の積み重ねにつながるため、長期保有を基本とする投資スタイルが推奨されます。また、一度にまとまった金額で購入することで、取引あたりの手数料率を下げられます。
加えて、証券会社の選択も重要です。一部の証券会社では、特定の米国ETFについて買付手数料が無料となる銘柄を取り扱っており、これらのサービスをうまく活用することで、投資コストを大幅に削減することが可能です。特に長期投資を前提とした積立投資にとっては手数料の違いが最終的なリターンに大きく影響してくるためしっかりと検討しましょう。
初心者が陥りやすい失敗パターンと対策法
初心者が陥りやすい失敗パターンがあります。一般的には、「短期的な値動きに一喜一憂して頻繁に売買を繰り返す」「一つの地域や銘柄に集中投資する」「手数料の高い商品を選ぶ」などが挙げられます。海外ETFのみならず汎用の対策としては、投資目的と時間軸を明確にすることが重要です。投資は長期的な視点で行うことが重要であり、短期的な市場変動に惑わされない姿勢が必要です。
また、投資前に十分な知識を身につけることも重要です。特に海外ETFの場合、時差や物理的距離などの問題で情報の格差が起こりやすいため、現地のメディアなどを活用した情報取集ができるとよいでしょう。初心者は複雑な商品(レバレッジ型ETFなど)は避け、S&P500などの主要指数に連動する流動性の高いETFから始めるのも良いでしょう。
さらに、投資金額は無理のない範囲に抑え、分散投資を心がけることでリスクを軽減できます。投資は自己責任で行う必要があり、投資可能な金額の範囲内で行うことが原則です。
おすすめの海外ETFと証券会社選び

海外ETFのデメリットとその対策を理解したところで、初心者に適した具体的な商品選びと証券会社選びのポイントを簡潔に解説します。
初心者に適した海外ETFの選び方と具体例
初心者には流動性が高く、分散投資が可能な商品がおすすめです。金融庁が投資初心者向けに推奨する書籍リストにも分散投資を勧める内容が多く含まれています。
例えば、S&P500連動ETFなどは適しているでしょう。流動性が高いうえに米国経済全体をカバーする構成で分散投資効果も得られるため、初心者でもリスクを抑えた投資を実践できます。また、同様の商品として全世界株式ETFも、地域分散により安定運用が期待できる選択肢です。
海外ETF取扱い数はもちろん付加サービスにも注目
SBI証券では506本の海外ETFの取り扱い(原稿執筆時点での内訳:米国ETF 463本、中国ETF 29本、韓国ETF 2本、シンガポールETF 12本)があり、一部銘柄は買付手数料が無料になっています。楽天証券では390本の海外ETFの取り扱い(原稿執筆時点での内訳:米国ETF/ETN 355本、中国ETF 22本、シンガポールETF 13本)があり、こちらも豊富な銘柄を扱っています。また、銘柄数だけでなく、手数料や情報提供の充実度も重要なポイントです。初心者は日本語情報の充実度や少額投資の可否も考慮するとよいでしょう。
まとめ

海外ETF投資は魅力がある一方で、為替リスク、二重課税問題、手数料負担、情報格差といったデメリットを理解することが重要です。しかし、恐れているばかりでは資産形成に後れを取ってしまいかねません。適切な対策を講じて賢く活かせば、海外ETFは新たな手札となります。長期にわたって付き合っていくうえでのはじめの一歩を、まずは踏み出してみませんか。